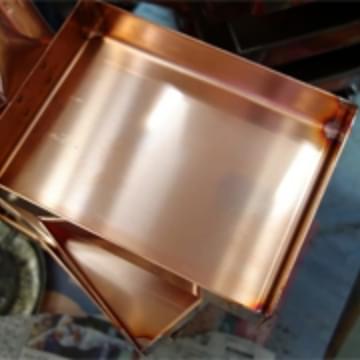Q
土鍋は届いたらすぐに使えますか?
A
使いはじめる前に、必ずおかゆを炊いてください。
おかゆのでんぷんで、素地の隙間や貫入をうめて、水漏れをおさえ、熱にならすことが目的です。
目の粗い伊賀の陶土を使い、職人さんが手ろくろで、土をひきのばしながら作った土鍋は、機械の型押しで陶土をつぶして作る量産型の土鍋と異なり、陶土に含まれていた空気をより多く保っています。
この空気があるおかげで、直接、火があたっているところばかりでなく、土鍋全体がゆっくりとあたたまり、その結果、食材本来のうまみを引き出します。
また、空気は保温性が高いため、一度、高温になると火からおろしても長時間冷めません。
この土楽さんの土鍋で、使いはじめにおかゆを炊く理由のひとつは、水漏れをおさえることです。目の粗い素地の隙間や窯に入れて焼いたときにできる貫入やひびを、おかゆのでんぷんでうめていきます。
でんぷんでめどめしないまま、水を入れて放置すると、極端に例えれば、植木鉢のようなもので、水が素地に浸透し、しみ出します。
おかゆを炊くもうひとつの理由は、熱にならして、よいひびや貫入を入れることです。
伊賀の陶土を使い、手ろくろで作った土鍋は、熱したときに膨張し、さめたときに縮む特徴を持つため、火にかけると、ひびや貫入が入ります。
細かいひびや貫入がいっぱい入ったほうが、熱したときのエネルギーが分散し、突然、大きな悪いひびが入ることを防いでくれます。
Q
火にかけるときに気をつけることは?
A
急激な温度変化に弱いため、火にかけるときは、弱火からはじめてください。
伊賀の目が粗く空気を多く含む土鍋は、空気と素地の膨張率が異なるため、突然、強い火にかけると、直接、強火が当たった部分の空気が先に膨張し、大きなひびが入ることがあります。
また、火に当たるところに水がしみこんでいると、水が沸騰する温度が、土鍋が膨張する温度よりも低いため、水が先に沸騰して大きなひびが入る原因になります。
土鍋はかならずよく乾かしてから火にかけてください。
火にかけるときは、最初は弱火で。
土鍋全体があたたまってきたら、中火に。
そして、強火に‥‥と、少しずつ温度を上げて行ってください。
Q
ひびがはいってしまったんですが大丈夫ですか?
A
ひびや貫入は、かならず入ります。
そのままご使用して頂いて問題ありません。
量産型の土鍋は熱したときの膨張を防ぐ目的で、陶土にペタライトという海外産のガラス質の石粉を混ぜて、素地の隙間や多孔質だった陶土の目に見えない細かいあなをふさいでいます。
多孔質を保った土楽さんの土鍋は、土鍋に含まれる空気によって、直接、火があたるところだけでなく、鍋全体がじっくりとあたたまり、一度、高温になるとさめにくく、保温性が高いことが特長です。
また、表面が均一でないため、直火で肉を焼くときも、肉が土鍋にぺたっとひっつくことなく美しく焼くことができます。
土楽さんでは、多孔質でなくなった土鍋は、土鍋のよさが失われていると考えて、ペタライトは使わないそうです。
この土鍋に含まれる空気と、釉薬がかかっているところ、素地は、熱したときの膨張率がそれぞれ異なるため、熱したときに膨張し、ひびや貫入が入り、さめたときに縮む特徴があります。
使えば使うほど、ひびや貫入が入り、煮えやすく、割れにくい、よい土鍋に育っていきます。
Q
水漏れしてきたらどうすればいいですか?
A
また、おかゆを炊くか、でんぷんを含む料理をしてください。
よいひびや貫入が入れば入るほど、煮えやすくじょうぶな土鍋に育っていく土鍋は、使いはじめだけでなく、長くお使いいただく間にも、多少水漏れします。
水漏れが気になったときは、おかゆを炊いてめどめをするか、雑炊、うどん、ラーメンなど、でんぷんを使った料理を作ってください。
釉薬のカケができて、水漏れが気になるときは、カケた部分にごはんつぶをすりこんで、一晩乾かしてください。ごはんつぶがノリの代わりになって水漏れを押さえてくれます。
Q
火加減のコツはなんですか?
A
最初は弱火から、徐々に強火にしていきます。
保温性が高いので、沸騰をしたら弱火でもグツグツ煮立ちます。
最初は弱火で、土鍋全体があたたまってから中火→強火と強めていきます。
沸騰したら弱火にします。
保温性が高いため、一度沸騰すると、強火でも弱火でも、ぐつぐつと煮えます。
食材や出汁、水などを入れたときは、温度が下がるので、火を強くします。
出汁を足すときに、冷たいものではなく、あたためたものを使うと煮立ちが早くなります。
Q
焦げ付いてしまったときは?
A
スプーン等でやさしくこすってください。
土鍋が乾いた状態で、スプーンで、こげているところだけを釉薬をはがさないように気をつけながら、やさしく何度もこすります。
Q
においがついてしまったときは?
A
お茶を使って消臭ができます。
お茶、もしくは、水と茶殻を入れて、弱火から少しずつ加熱して10分くらい煮立てます。
お茶の成分がいやな匂いを吸収してくれます。
Q
土鍋のしまいかたは?
A
ほかのうつわや鍋と重ねることは避けてください。
新聞紙がおすすめです。
フタと胴をじかに重ねるとキズの原因にもなるため、新聞紙をフタと胴の間にはさみます。
フタをひっくり返して重ねると場所をとりません。素材が異なるほかのうつわや鍋は重ねないでください。

土楽窯について
土楽窯は三重県伊賀の里に七代続く伊賀焼の窯元。
現在では伊賀の窯も機械化が進み、機械で量産する土鍋も増えていますが、「土楽」では、職人さんがろくろを回し、時間をかけて、手びねりでつくっています。
機械で作るかたちが均一な土鍋と違い、ひとつひとつゆがみや焼き色が違って、似ているけれど、他とは違う「一点もの」の土鍋ができあがります。
”食べるための器”として作られた土楽の土鍋は、大らかでありながら、美しいデザインのため、食卓にもそのまま出せるほどです。