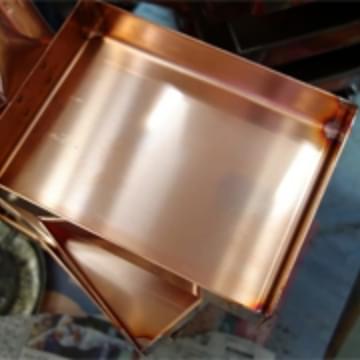使うほどに魅力が出る
土鍋を”育てていく”というご提案
土鍋は温まるまでは時間がかかりますが、一度温まったら冷めにくいと性質を持っています。
ゆっくり時間をかけて熱を鍋全体に行き渡らせてから、じわじわと加熱するため、肉や魚、野菜などの材料の持ち味を引き出し、柔らかくまろやかな味に仕上げます。
そんな土楽の土鍋は、使い込むことで温まりやすく、保温性・耐熱性が高くなります。
料理を土鍋のまま食卓に出せるデザインであることも魅力の一つ。
使い込むことで魅力が増す土鍋を、日々の生活の中で大切に使い込むことで、長い間使用できる土鍋に育てることができます。
使う前にやること
土鍋は使い始める前に、おかゆを炊く
おかゆを炊くことで、おかゆのでんぷんで、素地の隙間や貫入をうめて、水漏れをおさえます。そして、熱にならすことが目的のため、使用する前にはできるだけおかゆを炊いてください。
目の粗い伊賀の陶土を使い、職人さんが手ろくろで、土をひきのばしながら作った土鍋は、機械の型押しで陶土をつぶして作る量産型の土鍋と異なり、陶土に含まれていた空気をより多く保っています。
この空気があるおかげで、直接、火があたっているところばかりでなく、土鍋全体がゆっくりとあたたまり、その結果、食材本来のうまみを引き出します。
また、空気は保温性が高いため、一度、高温になると火からおろしても長時間さめません。
この土楽さんの土鍋で、使いはじめにおかゆを炊く理由のひとつは、水漏れをおさえることです。
目の粗い素地の隙間や窯に入れて焼いたときにできる貫入やひびを、おかゆのでんぷんでうめていきます。

でんぷんでめどめしないまま、水を入れて放置すると、極端に例えれば、植木鉢のようなもので、水が素地に浸透し、しみ出します。
おかゆを炊くもうひとつの理由は、熱にならして、よいひびや貫入を入れることです。
伊賀の陶土を使い、手ろくろで作った土鍋は、熱したときに膨張し、さめたときに縮む特徴を持つため、火にかけると、ひびや貫入が入ります。
細かいひびや貫入がいっぱい入ったほうが、熱したときのエネルギーが分散し、突然、大きな悪いひびが入ることを防いでくれます。
おかゆの炊き方

手順1
土鍋にごはん大さじ1と水を入れたら、すぐにガスの火にかけます。すぐに火にかけないと、めどめしていない土鍋から水が染み出してくる場合があるのでご注意ください。

手順1
土鍋にごはん大さじ1と水を入れたら、すぐにガスの火にかけます。すぐに火にかけないと、めどめしていない土鍋から水が染み出してくる場合があるのでご注意ください。

手順1
土鍋にごはん大さじ1と水を入れたら、すぐにガスの火にかけます。すぐに火にかけないと、めどめしていない土鍋から水が染み出してくる場合があるのでご注意ください。
POINT
おかゆは定期的に炊くことで、水漏れを防ぐことができます
よいひびや貫入が入れば入るほど、煮えやすくじょうぶな土鍋に育っていく土鍋は、使いはじめだけでなく、長くお使いいただく間にも、多少水漏れします。
水漏れが気になったときは、おかゆを炊いてめどめをするか、雑炊、うどん、ラーメンなど、でんぷんを使った料理を作ってください。
釉薬のカケができて、水漏れが気になるときは、カケた部分にごはんつぶをすりこんで、一晩乾かしてください。ごはんつぶがノリの代わりになって水漏れを押さえてくれます。
使い込むことで使いやすい土鍋にしていく
使うことで入る”ひび”を入れて使いやすい土鍋に
「ひびをいれる」なんて聞くと、「すぐ壊れてしまうのでは・・・?」と、よくご質問を頂きます。
そんな時当店では、「どんどん“ひび”を入れてください」とお答えします。
使うことで土鍋には必ずひびが入ります。そのひびが入ることで、土鍋が温まりやすく、熱に強くなっていきます。
ひびが入る理由
まず、何故ひびが入るのかということから説明すると、土楽では手作りの味わいを出すために、伊賀の粗い目の土を、均一化して使用していません。そのため素地に隙間が多く、目に見えない小さな穴がたくさん開いています。
この土鍋に含まれる空気と、釉薬がかかっているところ(色が付いている部分)、素地は、熱したときの膨張率がそれぞれ異なるため、熱したときに膨張し、ひびや貫入が入り、さめたときに縮む特徴があります。
土鍋に含まれる空気によって、直接、火があたるところだけでなく、鍋全体がじっくりとあたたまり、一度、高温になるとさめにくく、保温性が高くなります。
また、表面が均一でないため、直火で肉を焼くときも、肉が土鍋にぺたっとひっつくことなく美しく焼くことができます。使えば使うほど、ひびや貫入が入り、煮えやすく、割れにくい、よい土鍋に育っていきます。

焦げにくい土楽の土鍋
上記で説明したように、土鍋に使われる土とそこに含まれる空気により、土鍋の表面の膨張率が異なるため、直火でお肉を焼いても、土鍋にぺたっと張り付いてしまうことがなく、焦げ付きを抑えてくれます。
そのため、炒め料理など、通常フライパンで調理する料理も、同じように土鍋を使うことができるため、そのまま食卓に運ぶことができ、いつまでもアツアツの料理が楽しめます。
万が一、土鍋にこげがこびりついてしまった場合も、スプーンでやさしくこすることで、焦げを落とすことができます。(焦げによっては、こすっても落ちにくいのがありますので、力を入れず、時間をかけて落としてください。)


土楽窯について
土楽窯は三重県伊賀の里に七代続く伊賀焼の窯元。
現在では伊賀の窯も機械化が進み、機械で量産する土鍋も増えていますが、「土楽」では、職人さんがろくろを回し、時間をかけて、手びねりでつくっています。
機械で作るかたちが均一な土鍋と違い、ひとつひとつゆがみや焼き色が違って、似ているけれど、他とは違う「一点もの」の土鍋ができあがります。
”食べるための器”として作られた土楽の土鍋は、大らかでありながら、美しいデザインのため、食卓にもそのまま出せるほどです。